

歴史ある花街にたたずむ名店
北野天満宮東門前、京都最古の花街「上七軒」は、室町時代に北野天満宮再建の余った資材を使って7軒の茶店を建てたことに由来します。また、豊臣秀吉が北野で茶会を開いた際に献上した団子が大いに褒められ、その後花街として栄えました。第二次世界大戦でお茶屋の大半が転廃業しましたが、近年はお茶屋や芸舞妓が徐々に増えてきています。花街ならではの、はんなりとした風情溢れるたたずまい。
有職菓子御調進所「老松」は、この上七軒で1908年(明治41年)に創業した、風情溢れる佇まいの和菓子店です。

宝石の様に輝く金柑のお菓子
橙糖珠は、蜜漬けした金柑が詰まった美しい和菓子。金柑を10日間徐々に糖度を上げながら蜜漬けし、さらに「すり蜜」をあしらい出来上がります。すり蜜とは洋菓子ではフォンダンと言われ、明治に「本山」と訳された技法。溶かした砂糖を長い時間をかけてすりこぎで擂ることで生まれた美しい白色の衣装をまといます。凝縮された上品な金柑の味わいとほろ苦さ、そして程よい甘味が口の中で広がります。
お茶事の八寸としてはもちろん、普段のお茶菓子としても喜ばれる逸品です。

-
有職菓子御調進所 老松は有職儀式典礼にもとづく婚礼菓子、茶席菓子を中心に、たえず新しい菓子を生み出してまいりました。京菓子の伝統をふまえながら、形に素材に、絶えず新しい息吹を吹き込んでいます。
婚礼菓子、茶席菓子のほか、京都の歴史をふまえた風土菓や、「夏柑糖」に代表されるように、日本古来の原材料について考える菓子、「蓮根餅」や「香果餅」のように、菓子のルーツを求めてアジア各地を巡った結果生まれたもの、「流鏑馬」のように、芸能文化を伝承するための菓子など、菓子を通じて、歴史文化を次代へ継承するための試みを行っております。日本原産の作物や、古くから食されてきた素材に注目して、創菓した菓子は、古く、信仰の場において、神と人とをとりもつ大切な食べ物とされてきました。
人が集まるところに文化が生まれます。そんな「場」の文化にも菓子はつきもの。よって、菓子は人と人との間をとりもつコミュニケーションツールと考えています。
老松は菓子を通じて、京都の歴史と文化をお伝えして参ります。
(老松 代表取締役社長 太田 達)
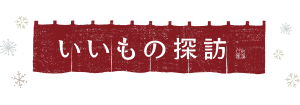




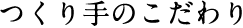

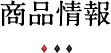
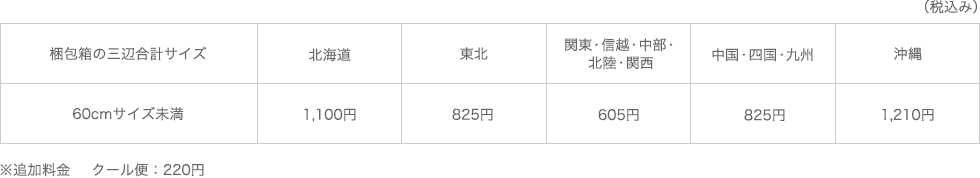


毎日糖度を少しずつ上げた蜜に入れ替えて蜜漬けにした金柑に、すり蜜をあしらった美しい和菓子。お茶事の八寸はもちろん、お茶うけとしても喜ばれる逸品です。