
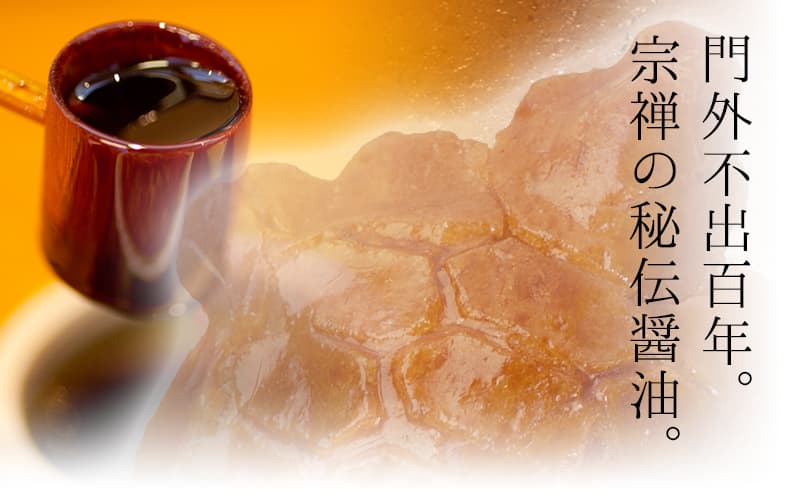
材料へのこだわり
自社で田を持つと、米が不作の年に、出来が悪い米でも使わざるを得なくなるため、宗禅では代々、田を持つことを許されておりません。
また、本当に品質の良い米でないと、亀のような複雑な紋様のあられは製造途中で割れてしまうため、創ることができません。
毎年新米の時期に店主自らが全国の餅米を探し求め、その年の最もあられに適した最高の餅米を吟味し、一年間使う米の品種と産地を選定しています。
また、長期熟成された底引きたまりに昆布やかつおの出汁と味醂を炊いて作り出す、門外不出の秘伝醤油を使用しています。
追い足して追い足して100年。代々、継承してきたことによる独特の旨味とあられに絡むとろみと濃度は絶品で、西京味噌や赤味噌柚子、南高梅、京山椒、わさびや和三盆等の素材との相性も抜群です。
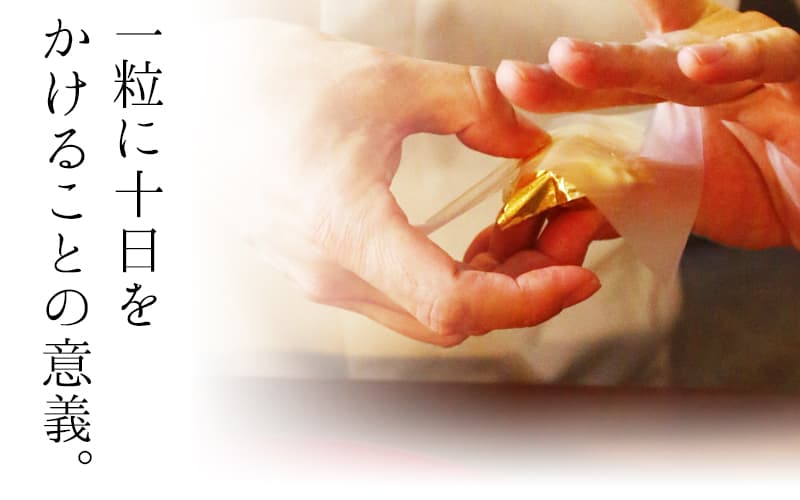
製法へのこだわり
菓匠 宗禅ではあられ一粒に10種類にもおよぶ工程を重ね、七日から十日という大変な手間と時間をかける「上技の匠」のもとで創り上げています。
「洗米」→「せいろ蒸し」→「餅つき」→「寝かせ」→「型抜き」→「筋入れ」→「天日干し」→「焼き」→「味付け」→「仕上げ乾燥」の過程で5度の選別を厳しく行い、ようやく完成します。
◆洗米
味がギュッとしまって、米の旨味が拡がるよう、洗米場を巨大な冷蔵庫で囲い、365日変わらず真冬同様の環境で米を洗い、そこから一晩、米を浸し置きます。
◆せいろ蒸し
高圧の水蒸気により、もち米を昔ながらの製法でゆっくり時間をかけて米を蒸しあげます。
◆餅つき
手水(てみず)を少なくして、しっかりつきあげることで餅の弾力が出てさらに米の風味が上がり、上技物あられ亀などの繊細な筋入れの過程で割れない餅生地の元となります。
◆寝かせ
つきあげた柔らかい餅を木箱に入れ、冷室で3日間ゆっくりと餅を熟成させ、旨味を凝縮し、餅を固めます。天候に応じて硬さが変動するため、型抜きと筋入れのタイミングを調整しています。
生地をスライスする際には食感を考慮し、厚みがあるザックリとした堅めのあられと、薄いサクッとした軽い歯触りのあられを作り分けています。
◆型抜き・筋入れ
餅生地を亀の型で抜き、に数ミリの絵柄となる溝を削ることを筋入れと言います。
溝を深く入れすぎると、乾燥時に割れてしまい、反対に浅すぎると、焼いた時に餅が四方八方に膨らみ、綺麗に仕上がりません。生地の硬さが季節、天候、温度、湿度に左右されるため、筋入れが上技師の技の真骨頂です。
◆乾燥
乾燥がうまくできないと餅生地の割れや焼いた時の膨らみに影響を及ぼします。独自の天日乾燥と室内乾燥を使い分けて餅生地の水分量を徹底管理しています。
◆焼き
まずは高温直火で少し火力を抑え低温で焼き始めます。何度も焼き窯から餅生地を出し入れし、空気を含ませるとともに、冷えた外気をあてることで、しっかりとあられの形を作りだします。
形が整うと火力をあげ、餅の芯に火が通るまでじっくりと焼き上げます。
そして最後にもう一度火力を下げて、ゆっくりと表面が黄金色になるまで焼き上げます。
この3段階の火力調整による焼成により、美しく綺麗なあられとなります。
◆味付け
生地が冷めきらないうちにドラムを回して秘伝醤油などで味付けします。
醤油があられに馴染んだ瞬間を見極めることで、仕上げ時にあられを割れから保護し、光沢と艶を出すことができます。
◆仕上げ
乾燥窯の中で真下から火を焚き、1時間ほどゆっくりと時間をかけてあられについた秘伝醤油などを乾かし、カリッとした食感に仕上げます。
ここまで一週間程かけて製造してきたことが無駄にならないよう慎重に作業して完成です。

- 元来あられは正月に神様に供えられた鏡餅から由来し、日本三大随筆の一つとされる「徒然草」に登場する事からも、日本元来の菓子として、また上流階級の嗜好品として重宝され、その中でも上技物あられは皇族への迎品・献上菓子とされてきました。
上技物あられ一粒創り上げるためには、蒸籠蒸しに、杵つき、天日干しに焼き上げと、7日から10日間という長い時間と手間がかかる昔ながらの製法を採用しています。
また、ケーキ等の洋菓子に用いられる小麦粉よりも10倍ほどする、最も適した高価な餅米が主原料です。
京西陣菓匠 宗禅は、「文明が進化し、職人の意義が薄れてゆく現代社会において、本物の技・味を追求し、後世により良き文化を継承する」事を使命に掲げ、日本唯一の上技物あられ処としての責務を全うするとともに、時代に迎合するのでは無く、これからも「文化」という二文字にこだわり続けていく所存でございます。
(菓匠 宗禅 当主 山本宗禅)
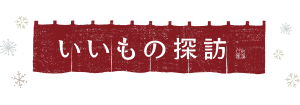






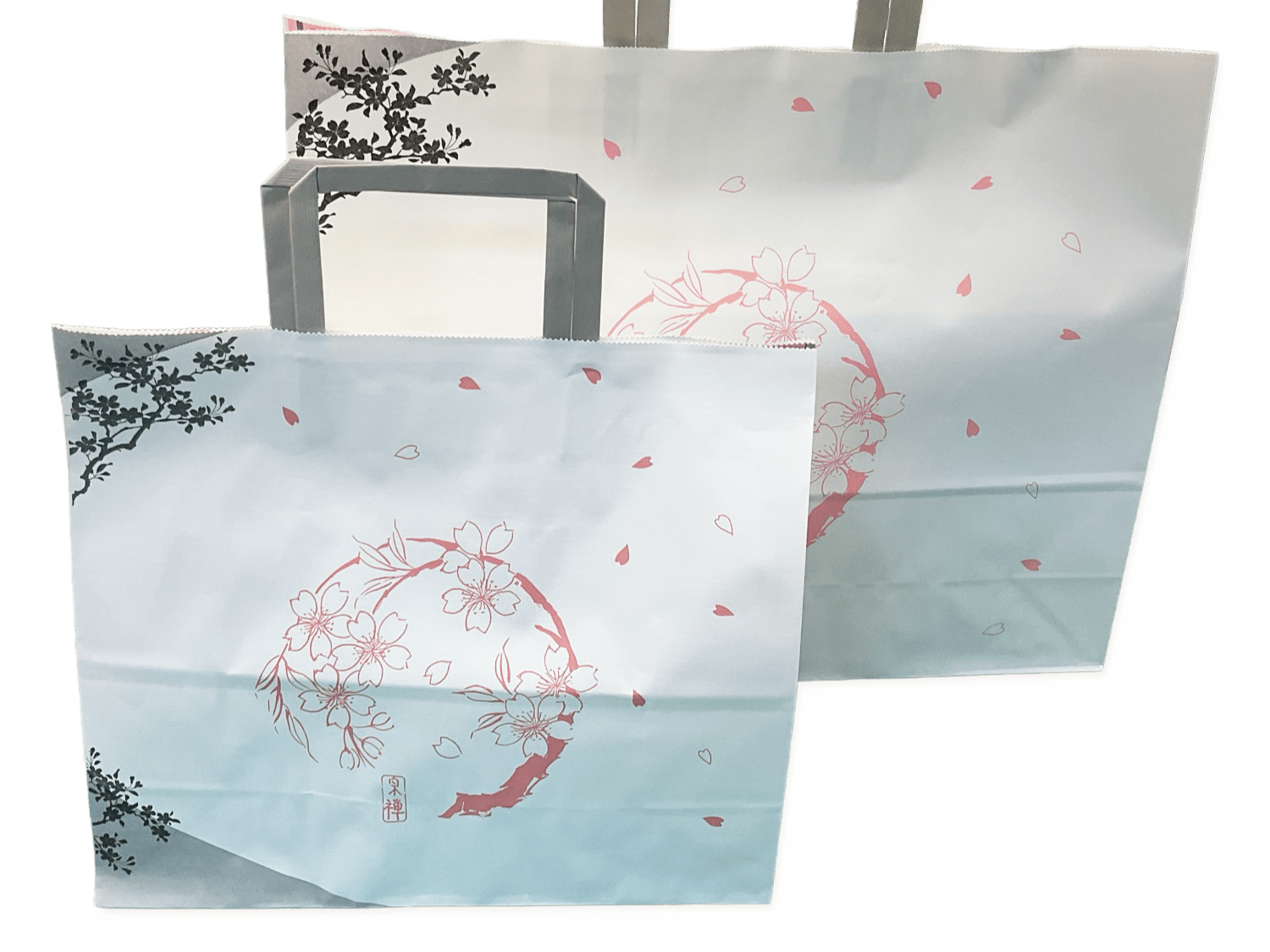
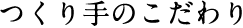

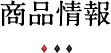



こだわりの素材を用いて伝統的な製法により作りあげた少し厚手のあられ。宇治抹茶、南高梅を用いた和三盆とざらめ、京七味など12種の味は、 四季折々に美しく移り変わりゆく京の12ヶ月を表現しています。